第二章:最適化アルゴリズムと冷たいサラダチキン
1. PDCAサイクルの空回り
森川誠(もりかわ・まこと)、三十四歳。人文学部准教授。
彼の腕には最新型のスマートウォッチが巻かれ、常に心拍数、睡眠の質、そして彼が最も恐れる「ストレスレベル」を計測している。
彼にとって、この地方大学は「非効率の博物館」だった。
「……従いまして、来年度のシラバス作成については、例年通り紙媒体での提出も併用し……」
学部長が抑揚のない声で読み上げる議案を聞きながら、森川は手元のタブレットで虚無の表情を隠していた。
(なぜだ。なぜクラウド共有を拒む? 『例年通り』という言葉は、思考停止の同義語ではないのか?)
森川の脳内では、高速でPDCAサイクルが回っていた。しかし、この会議室という物理的空間において、その回転は空気をかき混ぜる扇風機ほどの役割も果たしていない。
ふと、斜め向かいを見る。 只野教授だ。彼は窓の外を凝視している。
森川は知っている。只野教授が今、シラバスのことなど一ミリも考えていないことを。
おそらく、窓枠に止まった鳩の動きか、ガラスの汚れの形状を観察しているに違いない。
(只野先生……。あなたはなぜ、そのアナログな世界で平穏でいられるんですか)
森川は苛立ちと、ほんの少しの憧れがないまぜになった感情を抱きながら、強炭酸水を一口飲んだ。喉を刺す刺激だけが、彼を現実につなぎ止めていた。
2. デジタル・トランスフォーメーション(DX)の敗北
会議終了後、森川は只野を呼び止めた。
これは彼なりの啓蒙活動(およびストレス発散)である。
「只野先生。先ほどの会議、生産性が著しく低かったと思いませんか? 議事録の共有に三日かかるなんて、現代のスピード感じゃありません」
「やあ、森川先生。確かに長かったね。おかげで、窓の外の雲が『龍』から『崩れたソフトクリーム』に変わるまでを完全観測できたよ」
只野は悪びれもせず言った。
森川はこめかみを抑える。
「そういうことじゃないんです。先生、研究室の資料整理、まだ紙でやってますよね? スキャナ導入しましょうか? 検索性が段違いですよ。僕がセッティングしますから」
森川は善意の塊だった。
彼は本気で、この大学のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しようとしていた。
しかし、只野は困ったように眉を下げる。
「ありがとう。でもね、森川先生。紙には『重さ』と『匂い』があるんだよ。資料を探すとき、指先が紙の端を切る感触や、古いインクの匂いが、記憶のインデックスになることもある」
「……それは、非科学的なノスタルジーです」
「かもしれないね。でも、検索窓にキーワードを入れるだけじゃ、寄り道ができないだろう? 私は、探していないものを見つけるために、資料を探しているんだよ」
(セレンディピティ……偶然の幸運か) 森川は専門用語で翻訳し、ぐっと言葉を飲み込んだ。
論理的には森川が正しいはずだ。だが、なぜか只野の言葉には、分厚い古書のような説得力があった。
その時、大学の構内放送が流れた。 『全館、ネットワーク機器の不具合により、現在インターネット接続および学内サーバーへのアクセスができません。復旧の目処は……』
森川の顔色が青ざめる。
「嘘だろ……。次の講義のレジュメ、クラウドにしか上げてない」
現代っ子の学生たちは、Wi-Fiが死んだ瞬間にパニックになるだろう。
そして森川自身も、クラウドという外部脳を断たれれば、ただの「意識の高い服を着たおじさん」になり下がる。
「おや、それは大変だ」
只野は鞄から、あのアナログな、手書きの書き込みだらけのノートを取り出した。
「私は影響なしだ。森川先生、もしよかったら、私の予備のチョークをあげるよ。白と黄色、どっちがいい?」
森川は、只野が差し出した折れかけのチョークを呆然と見つめた。
バッテリー切れのない、最強のデバイスがそこにあった。
3. サラダチキンの味
夕暮れの研究室。 ネットワークは復旧したが、森川の精神的なバッテリーは底をついていた。
彼は夕食として、コンビニで買った「ハーブ味のサラダチキン」の封を切った。
高タンパク、低脂質。効率的な栄養摂取。しかし、今の彼にはそれが、ゴムの塊のように感じられた。
「コンコン」
ドアが開き、只野が顔を出した。 「森川先生、まだいたのかい」
「……ええ。サーバーダウンのせいで、仕事が後ろ倒しになりましたから」
只野は部屋に入ってくると、森川のデスクの端に、小さな包みを置いた。
「駅前の和菓子屋の『塩大福』だ。さっき店主と看板のフォントについて議論してたら、一つおまけしてくれてね。糖分は脳のガソリンだろう?」
「僕、夜は糖質制限を……」 言いかけて、森川は止めた。 目の前の塩大福は、粉をまぶされ、柔らかく沈み込んでいる。それは、彼のカチカチに最適化された生活とは対極にある存在だった。
「……いただきます」
一口食べる。餅の柔らかさと、餡の甘さ、そして微かな塩気が口の中に広がる。
スマートウォッチが『心拍数の低下』を通知した。リラックスしている証拠だ。
「美味しいですね」
「だろう? 効率も大事だが、たまには『余白』がないと、息が詰まるよ」
只野はふらりと部屋を出て行った。
森川は口元の粉を拭い、ディスプレイのスリープモードを解除した。 画面の光が戻る。
だが、さっきまでより少しだけ、画面の輝度が優しく見えた気がした。
「……明日は、B定食のアジフライにしてみるか」
森川は誰に言うでもなく呟き、冷たいサラダチキンをそっと脇へ追いやった。

第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
最終章
エピソード
論文抜粋
PR



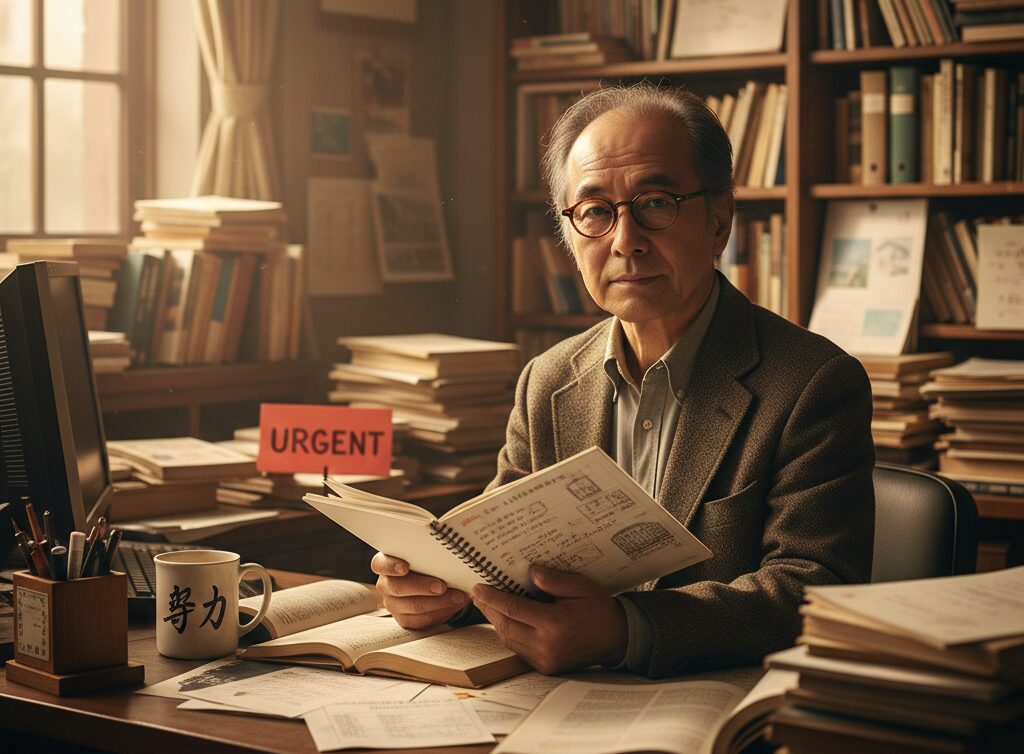

コメント