第七章:伝説のOBと「トマソン」の教え
1. スーツの来訪者
師走の只野研究室。暖房の効きが悪い部屋で、学生の佐藤と田中が卒論の追い込み(という名の現実逃避)をしていた時、ノックの音が響いた。
「失礼します。只野先生はいらっしゃいますか?」
入ってきたのは、ビシッと仕立ての良いスーツを着こなした、三十代半ばの男だった。手には有名ホテルの紙袋。いかにも「成功している社会人」のオーラを放っている。
「あれ、葛城(かつらぎ)さんじゃないっすか!」
田中が声を上げた。 彼は葛城亮介(かつらぎ・りょうすけ)。この研究室の卒業生で、現在は大手広告代理店のクリエイティブ・ディレクターとして活躍している、いわば「只野研の出世頭」だ。
「おお、田中君か。元気そうだね。先生は?」 「今、学内の『放置自転車』のサドル位置の計測に行ってます。あと十分くらいで戻るかと」 「ははは、相変わらずだなあ」
葛城は懐かしそうに笑い、埃っぽいパイプ椅子に腰を下ろした。
佐藤は興味津々で尋ねた。 「あの、葛城さんも昔、こういう変な研究してたんですか? 今の姿からは想像つかないんですけど」
葛城は苦笑いをして、自分のスマホを取り出した。 「これ、俺の卒論のテーマ。『都市における無用階段(純粋階段)の生態系』だ」
画面には、壁に向かって伸びるだけの階段や、昇った先が塞がれている階段の写真が映し出されていた。いわゆる「超芸術トマソン」と呼ばれる、不動産に付着した無用の長物だ。
「俺は一年間、これを探して東京中を歩き回ったよ。就活もせずにね」
2. 「赤コーン」事件
「只野先生は伝説だよ」葛城は語り出した。「俺たちの代で一番語り草になってるのが、『赤コーン事件』だ」
それは、十年前の冬のこと。 大学構内の工事現場にあった「赤いカラーコーン」が、ある日一つだけ行方不明になった。普通の教授なら気にも留めない。だが、只野教授は違った。
「『あのコーンには、作業員Aさんが書いたと思われる独特の「立入禁止」のフォントがあった。あれは文化遺産だ!』って大騒ぎしてね」
只野教授は、葛城たち学生を総動員して、大学中のゴミ捨て場や倉庫を捜索させた。 そして三日後、ついに用務員室の裏で、泥まみれになったそのコーンを発見したのだ。
「先生、それを見つけた時、泣いてたんだよ。『よかった、君はまだここにいたんだね』って、コーンを抱きしめて。俺たち、寒空の下で呆然としたよ。『この人は、赤いプラスチックの塊に、何を投影してるんだ?』って」
佐藤はドン引きしながらも、笑ってしまった。 「ヤバいですね、先生」
「でもね」葛城は真顔になった。「その時、先生が言ったんだ。『みんなが見過ごすゴミの中に、物語を見つけるのが僕たちの仕事だ』って」
3. 無駄が最強の武器になる
「社会に出るとさ、みんな『正解』ばかり求めるんだよ。効率、コスパ、タイパ。でも、みんなと同じ正解を出しても、誰も驚かないし、新しいものは生まれない」
葛城は、佐藤と田中の目を見て言った。
「俺が今の仕事で評価されてるのは、誰も気づかない『ノイズ』に気づけるからだ。人が『無駄だ』と切り捨てる部分にこそ、消費者の本音や、新しい企画の種が落ちている。それを教えてくれたのは、あの泥だらけのカラーコーンと、只野先生なんだよ」
佐藤はハッとした。 マンホールの拓本を取り、寄り道を推奨し、非効率を愛する教授。その全ての奇行が、実は「観察眼」という、AIにも真似できない最強のスキルを鍛えるトレーニングだったのかもしれない。
ガチャリ。 ドアが開き、只野教授が入ってきた。鼻の頭を赤くし、手には巻き尺を持っている。
「おや、葛城君。来てたのか」 「先生、ご無沙汰してます。お歳暮持ってきました」 「ありがとう。……ん? 葛城君、君のその革靴、左足の踵だけ減りが早いね。最近、また焦って歩いているんじゃないか?」
只野教授は、数年ぶりに会った教え子の顔を見るより先に、足元を見て言った。 葛城は驚き、そして嬉しそうに破顔した。
「参ったな。先生には隠し事ができないや。……そうなんです、ちょっとプロジェクトで詰まってて」 「そうか。なら、今日はお茶でも飲んでいきなさい。いい羊羹(ようかん)があるんだ。包み紙のデザインが昭和レトロでね……」
教授は、葛城が「大手広告代理店のエリート」であることなど意に介さず、ただの一人の「観察対象」として、そして「愛すべき教え子」として迎え入れた。
佐藤はその光景を見て、自分のスマホのメモ帳を開いた。 『私の武器:無駄なものを見つける力』 そう書き込んだ文字は、今までで一番、自分らしく思えた。

第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
第七章
最終章
エピソード
論文抜粋
PR



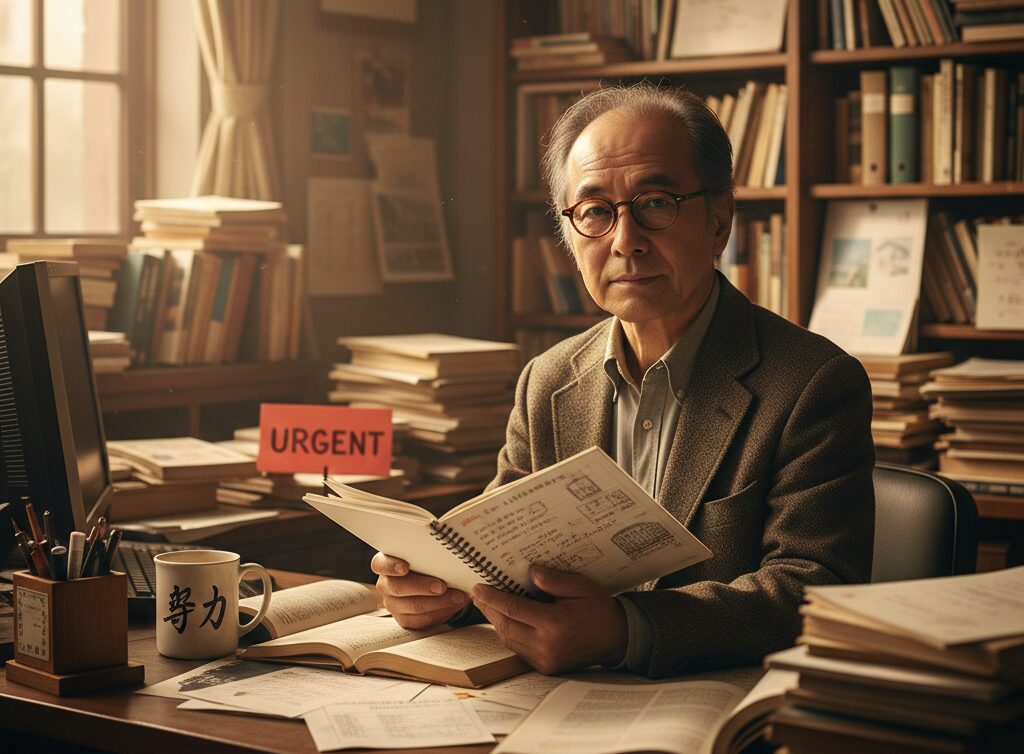

コメント