第三章:スマホ画面の向こう側とマンホール
1. エントリーシートと虚無
佐藤美咲(さとう・みさき)、二十一歳。人文学部三年生。
髪は流行りのインナーカラー(今は青)、ネイルは常に完璧。
インスタのストーリーは毎日更新。周りからは「人生楽しそうな大学生」に見えているかもしれない。
「……はぁ。マジ無理」
学内のカフェテリア。佐藤はテーブルに突っ伏して、スマートフォンの画面を睨みつけていた。
画面には、某大手企業のエントリーシート入力画面が表示されている。
『学生時代に最も力を入れて取り組んだこと(400文字以内)』
カーソルが点滅したまま動かない。
力を入れたこと? バイト? サークル? それとも、いかに効率よく単位を取るかの研究?
どれも嘘ではないけれど、400文字で熱く語れるほどの「何か」が、自分にあるとは思えなかった。
周りを見渡す。
隣のテーブルでは、リクルートスーツに身を包んだ四年生が、模擬面接のようなことをしている。彼らの声が、耳障りなノイズのように響く。
「自己分析とか、マジで意味わかんない。私って何?」
通知が鳴る。
インスタだ。高校時代の友達が、ハワイ旅行のキラキラした写真をアップしている。
「いいね!」を押しながら、佐藤の心は急速に冷えていく。
みんな、何者かになろうとして、着実に進んでいる。私だけが、この学食のぬるい空気の中に取り残されている気がした。
2. 中庭の怪しい影
気分転換に外の空気を吸おうと、佐藤はカフェテリアを出て中庭に向かった。 そこで、奇妙な光景を目撃した。
芝生の真ん中で、茶色いツイードジャケットを着たおじさんが、地面に這いつくばっている。
只野教授だ。
「……うわ、何してんの」
思わず声が出た。教授は、マンホールの蓋の上に白い紙を置き、その上から黒いクレヨンのようなものでゴシゴシと擦っている。
拓本だ。小学生の図工の時間以来、リアルでやってる人を見たことがない。
佐藤はおそるおそる近づいた。 「先生、何してんすか? まさか、それ研究?」
只野教授は手を止め、顔を上げた。
鼻の頭に黒い煤がついている。
「おや、佐藤君。これはね、昭和四十年製の『電電公社』時代のマンホール蓋だよ。
この『T字』の模様の摩耗具合が、この道の歴史を物語っているんだ」
教授の目は、ハワイ旅行の写真を見ている友達よりも輝いていた。
「……へぇ。それ、楽しいんすか?」
「楽しいとも。誰にも注目されない足元の歴史を記録する。これは一種のタイムトラベルだよ」
佐藤は呆れた。この人は、就活生の苦悩なんて知らずに、一生こうやってマンホールを擦って生きていくんだろうか。羨ましいというか、別世界の住人だ。

3. 寄り道のススメ
「君は、どうしたんだい? 眉間に皺が寄っているよ。まるで、ひび割れたアスファルトみたいだ」
教授が唐突に言った。ひび割れたアスファルトて。
でも、図星だった。
「……いや、ちょっと就活とか、将来のこと考えてて。
みんなすごいなって。
私、やりたいこととか特にないし、何に向いてるのかもわかんないし」
誰にも言えなかった弱音が、この変な教授の前だとスルッと出てしまった。
どうせ真剣に聞いちゃいないだろう、という安心感があったのかもしれない。
只野教授は、拓本の手を完全に止めて、立ち上がった。
そして、汚れた手をパンパンと払うと、佐藤の目をまっすぐに見た。
「佐藤君。君は今、目的地を決めなきゃいけないと思って、焦っているね」
「え、まあ。みんな決めてるし」
「私はね、路上観察をするとき、目的地を決めないんだ。
ただ歩く。そうすると、思わぬところで面白い看板を見つけたり、今日みたいに貴重なマンホールに出会えたりする」
教授は足元のマンホールを指さした。
「人生も同じじゃないかな。
最初から最短ルートでゴールを目指す必要はない。
寄り道をしたり、迷子になったりする中で、自分が本当に面白いと思える『何か』を拾うことだってある」
佐藤はポカンとした。 効率重視の森川准教授とは真逆のアドバイス。
でも、不思議と今の自分の心には、教授の言葉の方がスッと入ってきた。
「……寄り道、っすか」
「そう。君のその派手な髪色も、凝ったネイルも、今はまだ『寄り道』に見えるかもしれない。
でも、それがいつか、君だけの地図を描くための重要なランドマークになるかもしれないよ」
教授はニカッと笑った。
鼻の頭の煤のせいで、少し間抜けに見えたけれど、その笑顔は妙に温かかった。
4. 400文字のヒント
「さて、私は向こうの商店街の錆びたシャッターを調査しに行かねばならない。
じゃあね、佐藤君」
言うが早いか、只野教授は拓本の道具を鞄に詰め込み、風のように去って行った。
佐藤は一人、中庭に残された。 足元のマンホールを見る。
ただの鉄の塊だ。でも、教授にはこれが宝物に見えている。
「……変な人」
佐藤は小さく呟いて、スマホを取り出した。
例のエントリーシートの画面を開く。
『学生時代に最も力を入れて取り組んだこと』
佐藤は少し考えてから、フリック入力を始めた。
別に、すごいことを書かなくてもいいのかもしれない。
自分が面白いと思ったこと、夢中になった「寄り道」のことを、素直に書いてみよう。
『私は大学時代、様々な「寄り道」に力を入れました。
例えば、インスタグラムでの情報発信です。ただ流行りを追うだけでなく、自分の視点で切り取った日常を……』
指が動く。400文字が、少しだけ埋まりそうな気がした。 秋風が吹き、佐藤の青いインナーカラーの髪が揺れた。

PR



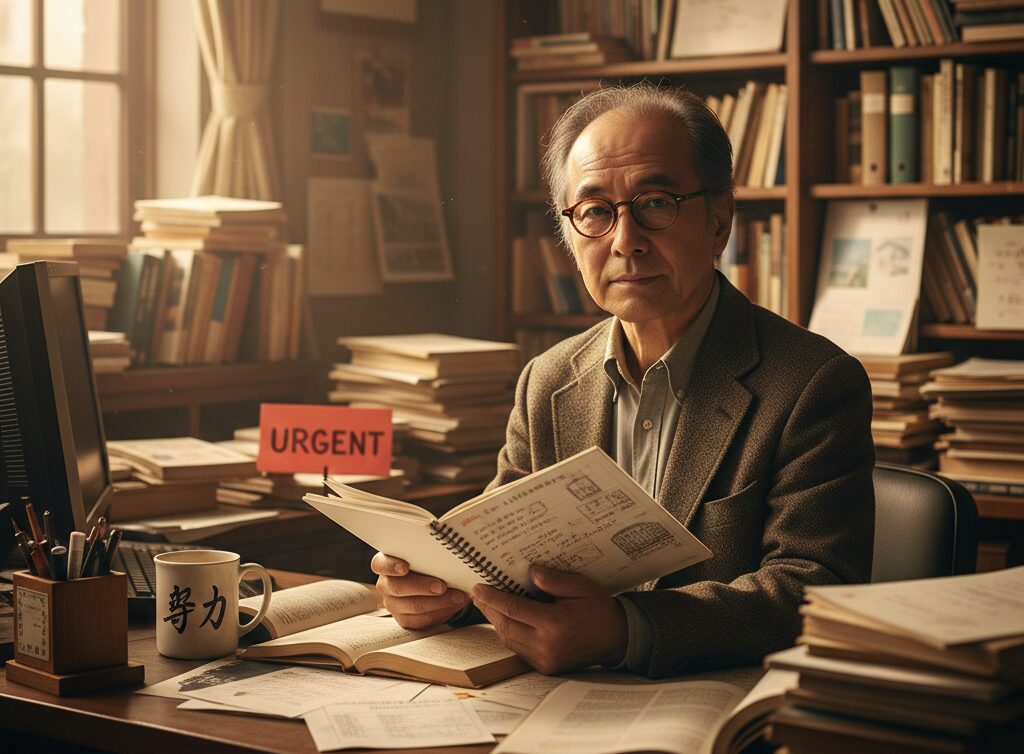

コメント