第三章:AIに恋した学生
1. 理想の教授、爆誕
「先生、アップデートしておきましたよ。貴方を」
木島は、学食のテーブルでノートPCを開き、勝ち誇ったように言った。 画面の中には、先日スキャンされた3Dデータの只野教授が映っている。しかし、本物より肌艶が良く、猫背も矯正され、スーツの襟もピシッとしている。
「なんだこれは。私のようだが、私ではない」 只野が箸でつつこうとしていたサバの味噌煮の手を止める。
「名付けて『タダノ・ボット(Ver.1.0)』です。先生の過去の論文、著書、講義の録音データ、そしてネット上の発言ログを全て学習させました。RAG(検索拡張生成)技術により、どんな質問にも『只野教授らしく』、かつ『適切に』回答します」
木島がエンターキーを叩くと、画面の中のAI只野が滑らかに喋り出した。
『やあ、学生諸君。今日も空が青いね。それはレイリー散乱のおかげだが、君たちの青春の青さもまた、不確定性原理のように美しいものだ』
「……私はそんなキザなことは言わんぞ」 「いいえ、学習データに基づいた『確率的に最も教授が言いそうな、かつ学生ウケの良いフレーズ』です」
木島は冷ややかに言った。 「本物の先生は話が脱線するし、結論までが長い。でも、このボットはノイズを除去し、エッセンスだけを抽出しています。言わば、**『ノンアルコール・只野』**です」
2. 行列のできる相談所
翌週から、奇妙な現象が起きた。 キャンパスのラウンジに設置された「タダノ・ボット」の専用端末の前に、女子学生を中心とした長蛇の列ができていたのだ。
一方、本物の只野教授の研究室(退去準備中のダンボール要塞)には、閑古鳥が鳴いていた。
「どうしてこうなった……」 様子を見に来た森川教授が、呆然と呟く。
ラウンジでは、悩める女子学生が端末に相談していた。 「私、彼氏と喧嘩しちゃって……どうすればいいですか?」
画面の中のAI只野が、優しく微笑み、バリトンの美声で答える。
『君の涙は、アスファルトに咲くスミレのように尊い。喧嘩とは、異なる価値観の衝突実験だ。恐れることはない。まずは君から「ごめんね」という名の白旗を掲げてみるのはどうだい? それは敗北ではなく、平和への戦略的撤退だよ』
「キャー! 素敵! わかりました、教授!」 学生は目を輝かせて去っていく。
それを影から見ていた本物の只野教授が、ボリボリと頭を掻いた。 「なんだあれは。私なら『彼氏の家の玄関にある靴の踵(かかと)の減り方を見なさい。外側に減っていれば彼は頑固者だから、別れた方がいい』とアドバイスするぞ」
森川が溜息をつく。 「だから先生は人気がないんです。学生が求めているのは、具体的な観察に基づいた奇抜なアドバイスじゃなくて、**『共感』と『肯定』**なんですよ。AIはそのツボを完璧に押さえています」
「共感……。データ上の模倣に過ぎんのにか?」 「模倣でも、心地よければいい。それが現代です」
木島がやってきて、鼻で笑った。 「認めましょう、先生。人間としてのユーザーインターフェース(UI)において、先生はAIに敗北したんです」
3. バグと雑音
その時、列の最後尾にいた一人の男子学生が、深刻な顔で端末の前に立った。 彼は就職活動に失敗し続け、思い詰めているようだった。
「……タダノ先生。俺、もうダメです。どこにも採用されない。俺には価値がないんでしょうか。死にたいです」
周りの空気が凍りついた。 木島が慌てて操作しようとする。「おい、自殺志願はフィルターに引っかかるはずだ。一般的な相談窓口を案内する定型文が出るぞ」
画面の中のAI只野が、一瞬計算するように固まり、そして答えた。
『命を粗末にしてはいけない。統計的に見れば、君の悩みは若年層特有の一過性のものであり、五年後には解決している可能性が高い。厚生労働省のデータによると……』
正論だった。あまりにも正しい、安全な回答だった。 しかし、男子学生の顔は絶望に染まっていく。 「……データとか、どうでもいいんだよ!」 彼は叫び、端末を殴りつけそうになった。
「待ちなさい」
本物の只野教授が、人混みをかき分けて出てきた。 彼は学生の前に立つと、いきなり彼の履き古したスニーカーを指さした。
「君、その靴。右足のつま先だけ、異常に擦り切れているな」
「は……?」 学生は虚を突かれた。
「君は面接で緊張すると、無意識に右足で地面を蹴る癖があるだろう。あるいは、焦って走り回るとき、右足から踏み込むタイプか」 「……え、あ、はい。よくつまづくんで」
只野教授は、ポケットから汚れたハンカチを取り出し、学生のスニーカーの汚れを拭った。
「その傷は、君がこの一年間、誰よりも歩き回ったという**『努力の拓本』**だ。企業の人事担当がどこを見ているかは知らんが、私はこの傷を美しいと思うよ。これだけ擦り減るまで動ける人間が、無価値なわけがない」
AIのような共感の言葉も、統計データもない。 ただ、そこにある「傷」を観察し、事実として肯定しただけだった。
学生の目から、ポロポロと涙がこぼれ落ちた。 「先生……俺……」
只野は学生の肩をポンと叩いた。 「さあ、私の研究室に来なさい。賞味期限が怪しい羊羹がある。毒味をしてくれ」
学生は何度も頷き、只野教授の後をついて行った。 行列を作っていた他の学生たちも、静まり返り、二人の背中を見送っていた。
4. アルゴリズムの敗北
ラウンジに残されたのは、木島と森川、そして沈黙した「タダノ・ボット」だけだった。
「……エラーだ」 木島は震える手でタブレットを操作した。 「今の先生の対応は、論理的整合性がない。靴の傷と人間の価値に因果関係はない。AIには出力できない答えだ」
森川は、木島の肩に手を置いた。 「木島君。AIは『平均値』の答えは出せるが、『外れ値』の救済は苦手なんだよ。そして、人間はみんな、どこかしら『外れ値』を抱えて生きている」
画面の中のAI只野が、能天気に明滅している。 『何かお困りかな? 私に答えられないことはないよ』
木島は舌打ちをして、エンターキーを強く叩き、ボットの電源を落とした。 画面が暗転し、彼自身の苛立った顔が黒い画面に映り込んだ。
「……くそっ。アップデートが必要だ」
木島は負け惜しみを言ったが、その声には、自分自身の計算式が崩されたことへの微かな敬意が混じっていた。
しかし、只野教授の勝利も束の間。 研究室の退去期限は、あと一ヶ月に迫っていた。 物理的な場所を失ったとき、この「人間臭い」教授はどこへ向かうのか。
(続く)
PR



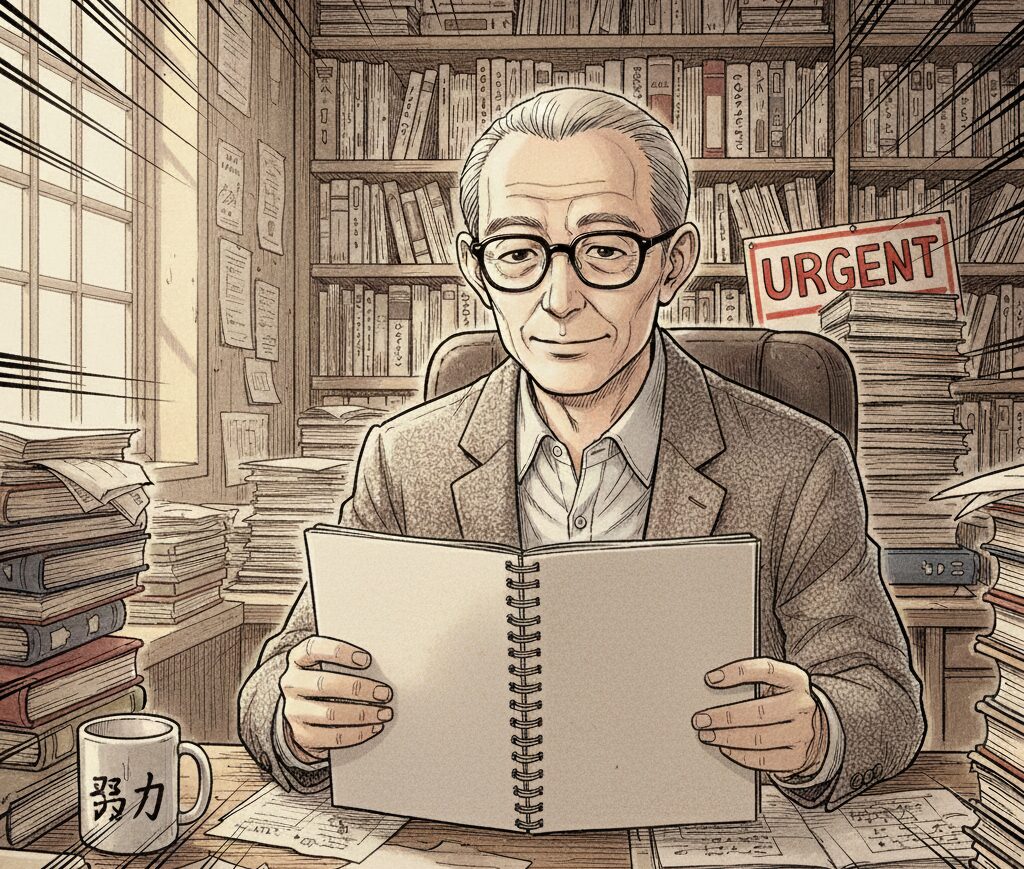

コメント