第四章:開かずのダンボールと、風景を記録する理由
1. 崩壊するカオス
三月末日。只野研究室の退去期限、最終日。
部屋はすでに「カオス」を通り越して「廃墟」と化していた。只野のコレクションの山は、すべて茶色のダンボールに詰め込まれ、床一面を覆っている。
「先生、午前中で搬出を完了させないと、明日から解体業者が入ります」
森川教授は疲労困憊の表情で、搬出業者を指揮していた。彼自身が設計した「効率的な番号付けシステム」も、只野の膨大な「路上採集物」の前では無力だった。
「森川先生、そう急かすな。ダンボールの『強度』と『経年劣化』の相関関係を研究するには、この重みを測る必要があるんだ」 只野は、積み上がったダンボールの山を、巻き尺と分度器で計測している。
そこへ、木島学生が、タブレットを片手に現れた。彼はこの引越しを「人類の非効率な活動の観察」として記録している。 「只野先生。先生の梱包方法の非効率指数は、平均的な引越しの7.2倍です。このままでは、AIセンターの建設に遅延が発生します」
「遅延こそが、時間という資源を味わう最良の手段だよ、木島君」
只野は言い返したが、彼の目はどこか上の空だった。彼の視線は、部屋の隅の、古びた本棚の奥に釘付けになっている。
2. 開かずのダンボール
すべてのダンボールが搬出され、研究室の床が初めて現れた。 しかし、本棚の最も奥、暖房器具の裏に隠されていた一つだけ、異質なダンボールが残されていた。
それは、他のダンボールと違い、三十年以上前のクラフトテープで厳重に封印され、表面は埃と湿気で黒ずんでいた。
「先生、これ。リストにありませんが、運びますか?」 搬出業者が尋ねた。
只野は、まるで触れてはならない聖遺物に触れるかのように、その箱に近づいた。
「いや、それは……」
只野は、明らかに動揺していた。彼は、この箱の存在を、自分自身からも封印していたようだった。
「何ですか、先生。マフィアの隠し金ですか?」木島が面白がって尋ねる。 森川は異変を察した。 「先生、もう時間がない。中身を確認して、廃棄か搬出か決めてください」
只野は覚悟を決めたように、ナイフを手に取り、テープの端に刃を入れた。テープがパチパチと音を立てて剥がれる。
蓋を開けると、中には予想通り「路上採集物」が入っていた。 だが、その採集物は、いつもの無機質なものではなかった。
色褪せた写真。それは、若き日の只野と、まだ学生だった妻・雅美が、笑顔で並んで写っている写真だった。そして、その写真の足元には、「恋愛成就祈願」と書かれた、汚れた絵馬が映っていた。
3. 「永遠に消えるもの」の研究
箱の中から出てきたのは、十数冊のノートと、大量の色鉛筆で着色された地図だった。
只野は、埃を払いながらノートを開いた。そこには、若き日の熱狂的な筆致で、**『都市に貼られた「別れ」と「永遠」のグラフィティ分析』**というタイトルが書かれていた。
「これは、私が大学院生のときに始めた研究だ。……雅美と出会ったばかりの頃の」
只野は、その中の一枚の地図を指さした。 「当時、このキャンパス周辺の壁やトイレには、若者たちが未来の自分たちに向けて書き残した、愛や夢の落書きが溢れていた」
『〇〇とXXは永遠に一緒』『必ず夢を叶える』
「私はそれを、**『不確かな未来への希望』**の記録として、日付と場所、筆圧まで記録していた。だが、一年後、大学の美化運動で、すべての落書きが白い塗料で塗り潰されてしまった」
只野の目には、遠い日の光景が映っているようだった。
「私はその時、深く絶望した。私の研究対象は、永遠に、完璧に**『消滅』**してしまった。雅美は言ったよ。『仁くん、あなたが記録したこと、その行為自体が、すでにその落書きの「永遠」なんだよ』と」
箱の底から、もう一枚、雅美の手書きのメモが出てきた。
「仁くんへ。この箱は、あなたが『消えてほしくない』と強く願った、唯一のものだね。だから、これはあなたの夢の『墓標』として、ここに封印しておきましょう。開けるのは、あなたが『消滅』を怖がらなくなった時だよ。」
— 雅美
只野は静かに目を閉じた。 そう、彼は「消滅」が怖かったのだ。愛する人との思い出、若き日の希望、そして、妻が信じてくれた「夢の記録」が、誰にも気づかれずに消えてしまうことが。
だから彼は、「すぐに消えないもの」、つまり、マンホールや標識、錆びた看板といった、無機質で安定したものを対象とする**「路上観察学」**へと転向したのだ。
4. 教授の「引越し」
只野は、深いため息をつき、顔を上げた。
「森川先生。木島君」 彼の声は、これまでの飄々とした調子とは違い、落ち着いていた。
「私は、ずっと『消滅』を恐れて、この部屋に閉じこもっていたのかもしれない。まるで、このダンボールの中身のように」
彼はその箱を、ゆっくりと閉じた。
「この箱は、廃棄する。代わりに、中身だけを覚えている」 「え、廃棄ですか?!」森川が驚いた。 「そうだ。記録とは、物質に残すことではなく、**『脳の記憶中枢』**に残すことだ。匂いと同じだよ」
只野は、最後に研究室の真ん中に立ち、天井を見上げた。カビのシミ、窓の隙間から差し込む光、古本と埃の匂い。そのすべてを、彼は深く吸い込んだ。
「ありがとう。私の偉大な師である、この部屋よ」
そして、彼はダンボールを業者に預けた。
只野教授の「引越し」は、単なる物理的な移動ではなかった。 それは、過去の「消滅」の恐怖を乗り越え、未来の「デジタル化」の波に、**「人間という名の記録媒体」**として立ち向かう決意の表明だった。
教授は、清々しい表情で、誰もいない廊下を歩き出した。 彼のポケットには、雅美の書いた小さなメモだけが、そっと仕舞われていた。
(続く)
PR



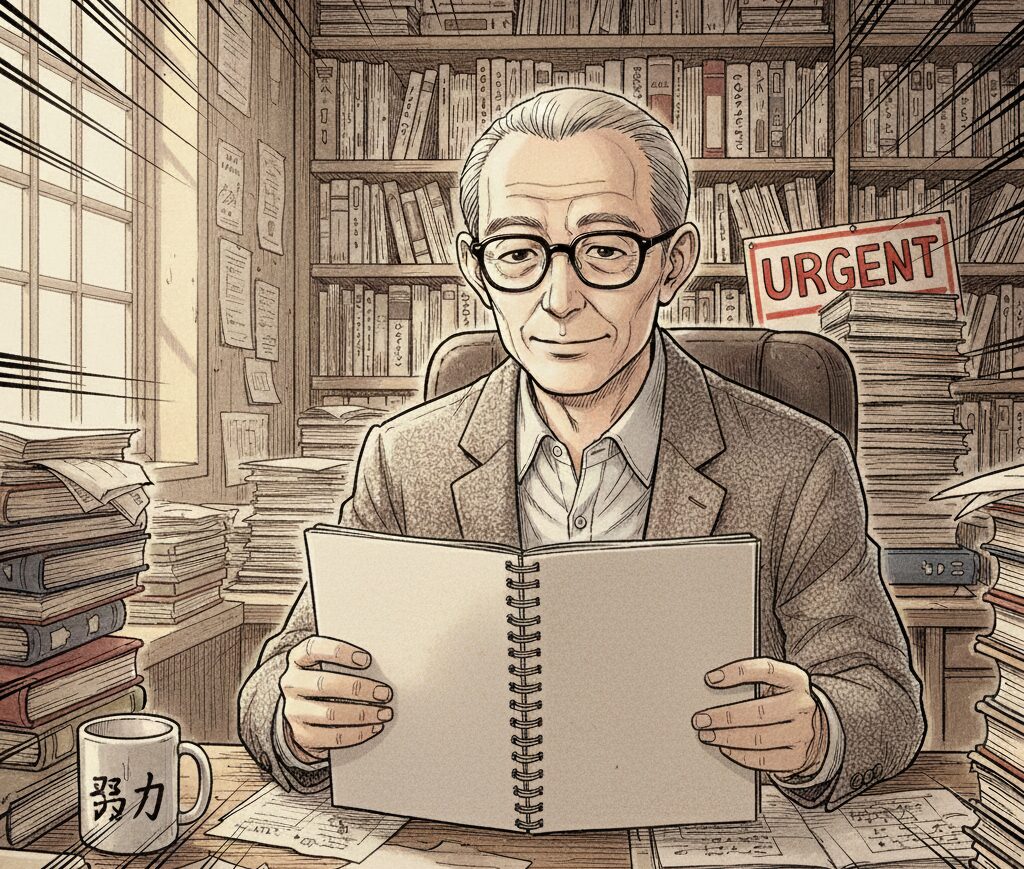

コメント