第二章:デジタル・アーカイブのパラドックス
1. 侵略者はレーザーと共に
その日の只野研究室は、まるでSF映画の撮影現場のようになっていた。
「いいですか、ミリ単位のズレも許されませんよ。この空間の『カオス』こそが、後世に残すべき資産なんです」
森川教授が、作業着を着た業者たちに指示を飛ばしている。 部屋の中央には、三脚の上に据えられた奇妙な球体の機械が鎮座し、赤いレーザー光線を四方八方に放っていた。
「3Dレーザースキャナーです」 森川は、部屋の隅で不服そうに腕組みをしている只野教授に説明した。 「この機械で研究室全体をスキャンし、点群データとして保存します。さらに、高解像度カメラでテクスチャを撮影し、VR空間に『バーチャル只野研究室』を完全再現するんです」
只野は鼻を鳴らした。 「バーチャル、か。幽霊の住処でも作るつもりかね?」
「未来への遺産ですよ。建物は壊されますが、こうすれば先生のコレクション配置や、本の山脈の角度に至るまで、永遠にクラウド上に残ります。学生たちがヘッドセットをつければ、いつでも『只野ワールド』に没入できる。完璧なソリューションです」
森川は自信満々だった。彼なりに、敬愛する先輩の研究室を救うために奔走し、予算をぶんどってきたのだ。
そこへ、スキャンを担当するベンチャー企業「アーカイブ・ノヴァ」の代表、佐伯(さえき)がタブレットを持って現れた。黒いタートルネックに無精髭、いかにもシリコンバレーかぶれといった風貌の男だ。
「森川先生、順調ですよ。オクルージョン(遮蔽)の問題も、AI補完でクリアできそうです。いやあ、このゴミ……じゃなくて資料の密度、データ量が半端ないっすね。燃えますよ」
佐伯は只野の方を向き、軽い調子で言った。 「教授、安心してください。僕らの技術なら、この部屋の『空気感』までコピーできますから」
「空気感、だと?」 只野の眉がピクリと動いた。
2. ノイズを除去するな
作業が始まって数十分後、事件は起きた。
「あ、ちょっとそこのスタッフさん。その本棚の裏のホコリ、スキャンのノイズになるからエアダスターで飛ばしちゃって」
佐伯の指示を聞いた瞬間、只野が叫んだ。 「待った!!」
只野はスタッフの前に立ちはだかり、本棚の裏を両手でガードした。 「何をしようとしている。このホコリを飛ばすとは正気か?」
佐伯はきょとんとした。 「え? いえ、綺麗なデータを作るためにゴミを除去しようと……」
「これはゴミではない! 『時間の堆積物』だ!」
只野は、棚の奥に積もった灰色の綿埃を指さした。 「いいかね。このホコリの厚みは、私がこの棚の奥にある『昭和六十年度・路上観察学会議事録』を、三十年間一度も開かなかったという動かぬ証拠なんだ。これを飛ばしてしまっては、この部屋の『停滞』という重要な文脈が失われる!」
佐伯は困惑して森川を見た。 「……森川先生、どういうことっすか? クライアントの要望は『綺麗なアーカイブ』ですよね?」
森川は頭を抱えた。 「あー……佐伯さん。只野先生にとっては、汚れや劣化も『情報』なんです。そのままスキャンしてください」
「マジすか。データ容量、倍になりますよ?」 「構いません。予算は追加します」
渋々作業を再開する佐伯たち。しかし、只野のチェックはさらに厳しくなった。 窓ガラスの汚れ(雨垂れの軌跡)を拭こうとすれば止められ、飲みかけのコーヒーカップ(カビ培養中)を片付けようとすれば「生態系の破壊だ」と怒鳴られる。
佐伯の額に青筋が浮かび始めた。
3. 匂いのない完コピ
数日後。 森川の研究室で、スキャンデータの試写会が行われた。
「見てください、このクオリティ。我ながら傑作です」 佐伯が自信満々に大型モニターに映像を映し出した。
そこには、只野研究室が映っていた。 本棚の歪み、机の上の傷、そして只野が死守したホコリに至るまで、恐ろしいほどの解像度で再現されている。 コントローラーを操作すると、画面の中を自由に歩き回ることができた。
「すごい……」森川は息を飲んだ。「本物と見分けがつかない。これなら、文句はないでしょう、只野先生」
只野は、じっと画面を見つめていた。 そして、静かに言った。 「……綺麗すぎるな」
「は?」佐伯が声を荒らげた。「解像度は8Kですよ? 汚れもそのまま残しましたよ?」
「違うんだ。佐伯君」 只野は自分の鼻を指さした。 「匂いだよ。この映像からは、あの部屋特有の、古本と湿気と、安物のインスタントコーヒーが混ざり合った、あの『饐(す)えた匂い』がしてこない」
佐伯は呆れて笑った。 「匂い? そりゃそうでしょう。これは視聴覚データなんですから。メタバースに嗅覚デバイスはまだ標準実装されてませんよ」
「だからダメなんだ」 只野はモニターを指差した。
「視覚情報だけの再現は、剥製(はくせい)と同じだ。形は完璧だが、命がない。君たちは、私の研究室の『死体』を作ったに過ぎない」
佐伯がついにキレた。 「アンタねえ! さっきから聞いてりゃ、こっちは最新技術で厚意でやってやってるんだよ! 匂いなんて、データ化して何の意味があるんですか!?」
部屋の空気が凍りついた。森川が仲裁に入ろうとしたその時、只野が静かに立ち上がった。
4. 記憶のトリガー
只野は、佐伯の持っていた高級そうな革の鞄を指さした。 「佐伯君。君はその鞄を大切にしているね。よく手入れされている」
「……ええ。亡くなった親父の形見なんで」 佐伯は不機嫌そうに答えた。
「その鞄を開けたとき、君は何を感じる?」
佐伯は一瞬、言葉に詰まった。 そして、ハッとした表情をした。 「……親父の、整髪料の匂いがするんです。それ嗅ぐと、なんか、昔怒られたこととか、急に思い出すっていうか」
只野は深く頷いた。 「そうだろう。視覚よりも嗅覚の方が、脳の記憶中枢(海馬)に直接届くと言われている。匂いこそが、記憶を呼び覚ます最強のトリガー(引き金)なんだ」
只野は画面の中の「バーチャル研究室」に背を向けた。
「このデジタルデータは素晴らしい。否定はしない。だが、私の研究室の本質は、あの部屋に入った瞬間に肺を満たす、カビ臭い空気にある。それが保存できない以上、これは『只野研究室』ではない。ただの『精巧な画像』だ」
佐伯は黙り込んだ。自分の鞄を無意識に撫でている。 彼の中の「効率化の鬼」と「人間としての情」が戦っているようだった。
「……負けましたよ」 佐伯はため息をつき、頭を掻いた。 「匂いは無理っす。今の技術じゃ、匂いの分子構造まで保存して再生するのはコストが天文学的になる」
「だろうね」只野は笑った。
「でも」佐伯は顔を上げた。「オプションで『環境音』は入れときました。先生がいつも聞いてる、窓の外の工事の音とか、古時計の秒針の音とか。それくらいなら、トリガーになりませんかね?」
モニターから、チクタク、チクタクと、あのアナログな時計の音が流れ始めた。 それは、無機質な3D空間に、ほんの少しだけ「時間」を取り戻させた気がした。
「……悪くない」 只野は目を細めた。 「少なくとも、無音の死後の世界よりは、居心地が良さそうだ」
森川は胸を撫で下ろした。 完全な保存は無理だとしても、只野とデジタルの間に、小さな「休戦協定」が結ばれた瞬間だった。
しかし、問題は解決していない。 物理的な研究室の消滅期限は、刻一刻と迫っていた。
(続く)
PR



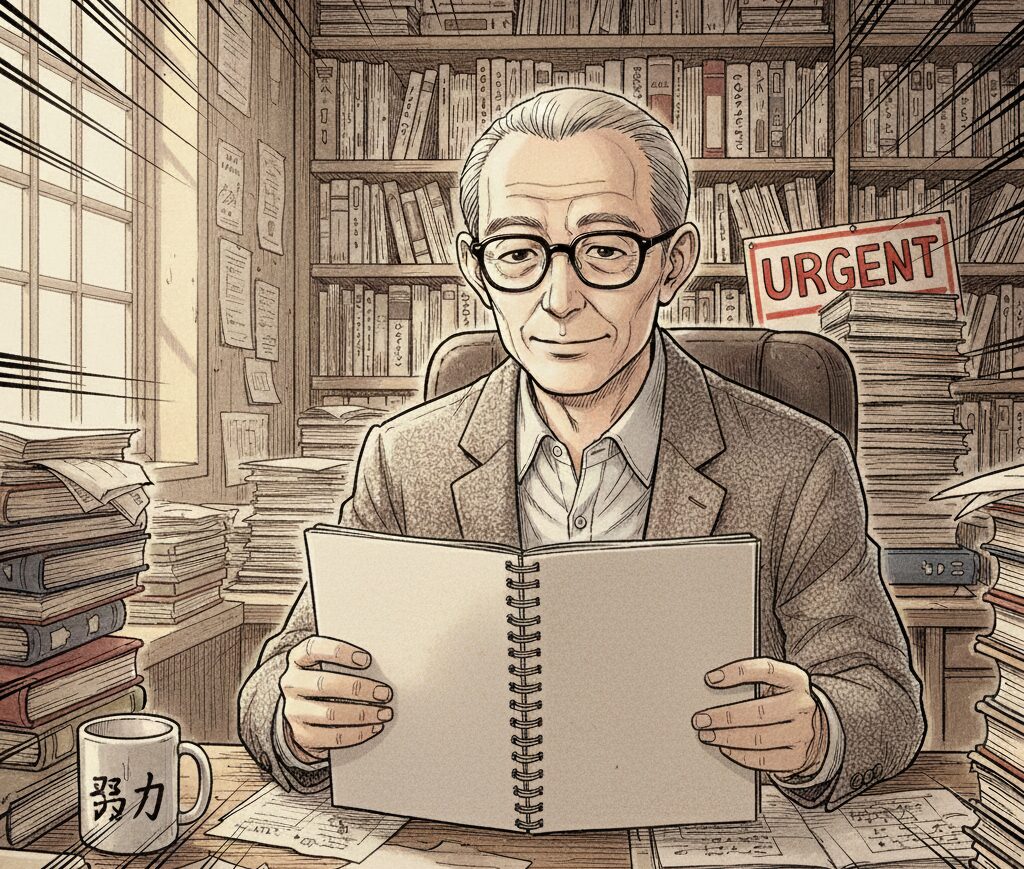

コメント